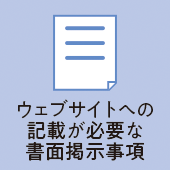ウェブサイトへの掲載が必要な書面掲示事項
入院基本料に関する事項
※タイトルをクリックすると詳細内容をご確認いただけます。
-
各病棟の看護職員等の勤務配置と受け持ち患者数について
当院2F病棟は、障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料)44床になります。
1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
・9時00分~17時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は7人以内です。
・17時00分~翌朝9時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は14人以内です。当院3F病棟は、障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料) 48床になります。
1日に14人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
・9時00分~17時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は6人以内です。
・17時00分~翌朝9時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は15人以内です。当院4F病棟は、回復期リハビリテーション病棟入院料2 50床になります。
1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と
5人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
・9時00分~17時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は10人以内です。
・9時00分~17時00分まで看護補助者1人当たりの受持ち数は10人以内です。
・17時00分~翌朝9時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は16人以内です。
専従の理学療法士3名以上・作業療法士2名以上・言語聴覚士1名以上・社会福祉士1名以上、専任の常勤医師1名以上・管理栄養士1名以上を配置しています。当院5F病棟は、回復期リハビリテーション病棟入院料2 41床になります。
1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と
4人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。
・9時00分~17時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は8人以内です。
・9時00分~17時00分まで看護補助者1人当たりの受持ち数は10人以内です。
・17時00分~翌朝9時00分まで看護職員1人当たりの受持ち数は18人以内です。
専従の理学療法士3名以上・作業療法士2名以上・言語聴覚士1名以上・社会福祉士1名以上、専任の常勤医師1名以上・管理栄養士1名以上を配置しています。当院はどの病棟も患者様の負担による付き添い看護は、行っていません。
-
入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理対策・褥瘡対策・栄養管理体制 意思決定支援及び身体拘束の最小化について
入院の際に医師や看護師をはじめとする関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、入院後7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援および身体的拘束の最小化についての基準を満たしています。
-
院内感染対策の為の指針
1.院内感染対策指針の目的
この指針は、院内感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、当院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。2.院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止を図り、アウトブレイク発生の際にはその原因の速やかな特定・制圧・終息を図ることは、病院として重要な役割である。本指針は院内感染防止策を全職員が理解・把握し、病院の理念に沿った安全な医療が提供できるよう基本的事項を定めたものである。3.院内感染防止対策のための委員会に関する基本的事項
院内感染防止対策委員会
社会医療法人明生会明生第二病院感染防止対策委員会規定に基づき、各部門の代表を構成員とする感染防止対策委員会を設置し毎月1回定期的に会議を開催し、院内感染対策に関する審議・決定を行う。緊急時は臨時会議を開催する。4.院内感染防止対策のための研修に関する基本方針
院内において感染防止対策に関する知識・技能習得のための研修会を年2回開催する。 さらに、必要に応じて臨時開催する。院外においても院外の研修会に積極的に参加する。5.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、その結果を院内感染防止対策委員会に報告する。6.院内感染発生時の対応
院内感染の発生時は、その状況及び患者様への対応を速やかに病院長に報告する。院内感染防止対策委員会は、臨時で委員会を招集し、発生原因の究明及び対応策を立案する。また、対応策の実施に向けた全病院職員への周知徹底を図り早期終息に努める。保健所等への 行政機関に適時相談し、技術的支援を得るように努める。7.患者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者様及びその家族からの閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。8.その他の院内感染防止対策の推進
当病院の職員は自らが感染源とならないために、自己管理を行い、病院感染対策マニュアルを遵守する。 -
医療安全管理体制の為の指針
第1章 総則
(安全管理指針)
第1条
この指針は、医療事故の予防・再発防止対策並びに発生時の適切な対応など社会医療法人明生会明生第二病院(以下「当院」)における、医療安全管理に関し必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全で質の高い医療の提供に資することを目的とする。(医療安全管理のための基本的な考え方)
第2条
医療安全は医療の質にかかわる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、当病院およびその職員一人一人が医療安全の必要性・重要性を病院及び自分自身の課題と認識し、医療安全体制の確立を図り、安全な医療の遂行を徹底する事が重要である。このため、当病院は医療安全管理者及び医療安全管理対策委員会を設置し、医療安全体制を確立するとともに、院内の関係者と協議のもと、本医療安全管理規程及び医療事故防止対策マニュアルを作成する。また、インシデント事例及び医療事故の評価分析により医療事故防止対策マニュアル等の定期的な見直しを行い、医療安全管理の充実を図る。第2章 医療安全体制
(医療安全管理者の配置)
第3条
医療安全管理の推進のため、医療安全管理者を置く。
1.医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有するものとする。
2.医療安全管理者は、医療安全管理対策委員会と連携・協同し業務を行う。
3.医療安全管理者は、以下の業務を担う。
1)院内報告制度を基盤とした医療安全のための活動
2)医療安全のための委員会に関する活動
3)医療安全のための部署間の調整、対策の立案と推進
4)医療安全のための旨針やマニュアルの作成
5)医療安全に関する研修・教育
6)医療安全に関する院外からの情報収集と対応
7)医療安全のための院内評価業務
8)事故発生時の対応業務(医療安全管理対策委員会の設置)
第4条
院内の全部門の事故防止のために、全体委員会として医療安全管理対策委員会を設置する。
1.医療安全管理対策委員会の委員長は院長とする。
2.医療安全管理対策委員会の委員は医療安全管理者および各部門から選ばれた者とする。3.医療安全管理対策委員は、各部門の医療事故対策の責任者として、以下の業務を行う。
1)各担当部署のインシデント報告の把握並びに、原因分析及び対策を検討する。
2)部署の医療安全推進のために担当職員を指導する。
3)部署の医療安全推進のために設備・備品・マニュアル等の整備保守点検を行う。
4)医療安全管理対策委員会の決定事項の各部署への周知徹底をする。
5)再発防止策の啓発、徹底、評価活動を行う。
4. 委員会の開催は毎月第4月曜(第5月曜)15:00~とする。ただし、必要に応じ、
臨時の委員会
を開催出来るものとする。(リスクマネージャーの設置)
第5条
第1条の目的を達成するため、医療安全管理対策委員会の下に各部門から選任された
リスクマネージャーを置く。
1.リスクマネージャーは医療安全管理対策委員会において決定した方針、医療事故防止対策、改善策等を現場に周知徹底させるとともに、相互に連携し情報交換や連絡調整を行う。
2.リスクマネージャーはインシデント・アクシデントの発生原因、傾向の分析、改善策等を検討し提言する。
(医薬品安全管理責任者)
第6条
当院は、医薬品の使用に際して、医薬品の安全使用のための体制を確保し、医薬品に係る安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理責任者を置く。
1.医薬品安全管理責任者は次の業務を行う。
1)医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
2)従事者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
3)医薬品の業務手順に基づく業務の実施
4)医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、そのたの医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
5)医薬品の安全使用のための業務手順書を必要に応じ、改定し順守を促す。
6)その他、医療安全管理に関する事項。(透析機器安全管理責任者)
第7条
透析治療を受ける患者に安心して安全な治療を提供することを目的とし、透析機器に係る安全管理のための体制を確保するために透析機器安全管理責任者をおく。
1.透析機器安全管理責任者は、院長の命を受け、透析治療を受ける患者に対し安全な治療を提供できるように機器・物品・薬剤・透析液などの管理・検討を行う。
2.透析機器安全管理責任者は検討結果を必要に応じて医療安全管理委員会に報告する。
3.新たな情報を得た場合には、その都度、関係する所轄会議へ情報提供を行い、連携をはかる。(患者窓口の設置)
第8条
患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保し、患者等との情報共有を確実なものとするために、施設内に患者相談窓口を常設する。
1.患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者およびその責任者、対応時間帯等について、患者等に明示する。
2.相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
3.苦情や相談で医療安全にかかわるものについては、医療安全管理者に報告し、当該施設の安全対策の見直し等に活用する。(医薬品安全管理責任者の配置)
第9条
1.医薬品安全管理責任者は、薬局長とする。
2.医薬品に関する十分な知識を有する老とする。
3.医薬品安全管理責任者は医薬品の安全使用にかかる業務のうち、以下の業務について主要な役割を担う。
1)医薬品の添付文書の情報のほか、医薬品製造販売業者、行政機関、学術誌等からの情報収集・管理
2)当該情報にかかる医薬品を取り扱う職員への周知
3)医薬品の業務手順に基づき、業務が行われているかについて定期的な確認と記録
4)その他、医薬品の安全使用に関する事項(医療機器安全管理責任者の配置)
第10条
1.医療機器の保守点検、安全使用の確保等の推進に資するため、医療機器安全管理責任者を置く。
2.医療機器安全管理責任者は、臨床工学技士長とする。
3.医療機器安全管理責任者は、医療機器の安全使用にかかる業務のうち、以下の業務について主要な役割を担う。
1)職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
2)医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施
3)医療機器の添付文書及び取扱説明書の管理、並びに医療機器の不具合情報や安全性情報の一元管理と従業者への周知
4)その他、医療機器の安全使用に開する事項(職員の責務)
第10条
当院のすべての職員は業務の遂行に当たっては、常日頃から医療の安全を確保することを自覚し事故防止のために細心の注意を払わなければならない。
1.医療事故ならびにインシデント事例を経験、もしくは発見した場合は、医療事故報告書またはインシデント報告書に記載し、翌日までに所属部署の責任者に報告する。
2.所属部署の責任者は、提出された上記の報告書を所定の期日ごとに委員会に報告する。
3.上記の報告書を提出したもの、あるいは体験した者に対して報告を理由に不利益な処分は行わない。
4.上記の報告書は総務課で保管する。
5.重大事故(報告基準レベル4・5の発生やその患者からクレームを受けた場合は、発生部門の責任者・看護師長または所属責任者に速やかに報告し、上位者の判断のもと患者の治療を優先するとともに、規定の報告ルートで速やかに医療事故担当責任者と院長に報告する。 -
身体拘束最小化のための指針
1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、従業員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、 緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。2.基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体拘束の実施を禁止する。この指針でいう身体拘束は、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、 その運動を抑制する行動の制限をいう。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
①緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の「3要件」をすべて満たした場合に限り、 必要最低限の身体拘束を行うことができる。
「切 迫 性」
患者本人または他の患者の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
「非代替性」
身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
「一 時 性」
身体拘束が必要最低限の期間であること。
②緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記「3要件」については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族 等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
③身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束最小化のためのマニュアル」に準じる。
(3)身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等禁止の行為の対象とはしない。
・整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
・身体拘束等をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
①離床センサー ②赤外線センサー ③起き上がりセンサー
(4)日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を感じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
①患者主体の行動、尊厳を尊重する。
②言葉や応対などで患者の精神的な自由を妨げない。
③患者の想いをくみとり、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
④身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
⑤薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を
予防する。
(5)向精神薬等薬剤使用上のルール
薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、
同意を得て使用する。
①不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、
対応する。
②行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を
行い、 患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。3.身体拘束最小化のための体制
(1)身体拘束最小化チームの設置 院内に身体拘束最小化対策に係る「身体拘束最小化チーム」(以下「チーム」という。)を設置する。
①チームの構成 医師、看護師、薬剤師、メディカルソーシャルワーカー、事務員等のメンバーをもって構成する。(身体拘束最小化チーム委員名簿参照)
②チームの役割
1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む従業員に定期的に周知徹底する。 2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
3)定期的に本指針・マニュアルを見直し、従業員へ周知して活用する。
4)身体拘束最小化のための従業員研修を開催し、記録する。4.身体拘束最小化のための従業員研修
医療・ケアに携わる従業員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。
①定期的な教育研修(年1回)の実施(新規採用時にも必ず実施する。)
②その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録5.身体拘束を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
①記録、集計、分析、評価を専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
②緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む
多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
③医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。
ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
説明内容:1)身体拘束を必要とする理由
2)身体拘束の具体的方法・理由
3)身体拘束を行う時間又は時間帯・期間
4)身体拘束による合併症
5)改善に向けた取り組み方法④患者・家族の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
⑤身体拘束中は、身体拘束の態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
⑥身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体拘束を行う「3 要件」を踏まえ、 継続の必要性を評価する。
⑦医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。
⑧身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。6.この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、従業員が閲覧可能とするほか、 当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族等が閲覧できるようにします。 -
個人情報保護法に関する利用目的の為の掲示について
【個⼈情報保護法に関する利⽤⽬的の掲⽰について】
明生第二病院では患者さんの個⼈情報保護に全⼒で取り組んでいます。
保管させていただいた個⼈情報につきましては以下の⽬的のために利⽤させていただく ことがあります。もし同意いただけない事項がある場合には、その旨をお申し出ください。 お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていた だきます。これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
★医療の提供に必要な利⽤
• 当院での医療サービスの提供
• 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
• 他の医療機関等からの照会への回答
• 患者さんの診療のため、外部の医師等の意⾒、助⾔を求める場合
• 検体検査業務の委託その他の業務委託
• ご家族等への病状説明
• その他、患者さんへの医療提供に関する利⽤
★診療費請求のための事務
• 当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務及びその委託
• 審査⽀払機関へのレセプトの提出、厚⽣労働省に提出するレセプトデータや、DPCデータを外部に依頼する場合があります。その場合は、法令・ガイドラインに則り、 適切に匿名加⼯処理を⾏いますので、特定の個⼈が識別されることはありません。 審査⽀払機関⼜は保険者からの照会への回答
• 公費負担医療に関する⾏政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
• その他、医療・介護・労災保険及び公費負担医療に関する診療費請求のための利⽤
★当院の管理関連業務
• 会計、経理、医療安全管理業務、⼊退院藤の管理運営業務
• その他、当院の管理運営業務に関する利⽤
★その他
• 企業等から委託を受けて⾏う健康診断等における企業等へのその結果の通知
• 医師賠償責任保険など医療に関する専⾨の団体、保険会社等への相談⼜は届出等
• 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
• 当院内において⾏われる医療実習への協⼒
• 医療の質の向上を⽬的とした当院内での症例研究
• 外部監査機関への情報提供 • 院内がん登録への利⽤、地域がん登録への情報提供
※個⼈データの漏洩等が発⽣し個⼈の権利利益を害する恐れのあるときは、個⼈情報保護 委員会へ報告・対応を協議の上、本⼈へ通知いたします -
近畿厚生局への届出事項に関する施設基準等
●基本診療料の施設基準等
・回復期リハビリテーション病棟入院料2
・障害者施設等入院基本料(10対1)
・特殊疾患入院施設管理加算
・後発医薬品使用体制加算3
・データ提出加算2
・診療録管理体制加算3
・入院ベースアップ評価料35
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)●特掲診療料の施設基準
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
・CT撮影及びMRI撮影
・施設入居時等医学総合管理料
・人工腎臓1
・導入期加算1
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算●その他届出に関する事項
・入院時食事療養(Ⅰ)
・酸素購入価格(1ℓ当りの単価)[可搬式液化酸素容器(LGC)0.23円、小型ボンベ1.98円] -
入院時食事療養に係る届出
当院は厚生労働大臣が定める基準による 食事療養を行っている保険医療機関です。
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
治療・病状等により、別に厚生労働大臣が定める特別食 を提供しております。 -
明細書の発行状況に関する事項について
当院では,医療の透明化や患者様の情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で 発行することと致しました。
なお明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、 その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 -
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に取り入れており、 後発医薬品使用体制加算を算定しております。
ご不明な点につきましては、当院医師または薬剤師にお尋ねください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、 同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。
■医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整えております。■医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者様にご説明いたします。
-
医療情報取得に関する事項
当院はオンライン資格確認の導入医療機関です。
健康保険証と紐づけされたマイナンバーカードを使用して、専用端末よりオンラインで 保険証の資格情報等を確認することができる制度です。
・加入している医療保険
・有効期限
・会計時の診療費の負担割合や上限額等